建設業界あるある
日本全国津々浦々、人の営みあるところに建設や土木の現場あり。
知っているようで知らない「あるある」がたくさんあるんです。
-
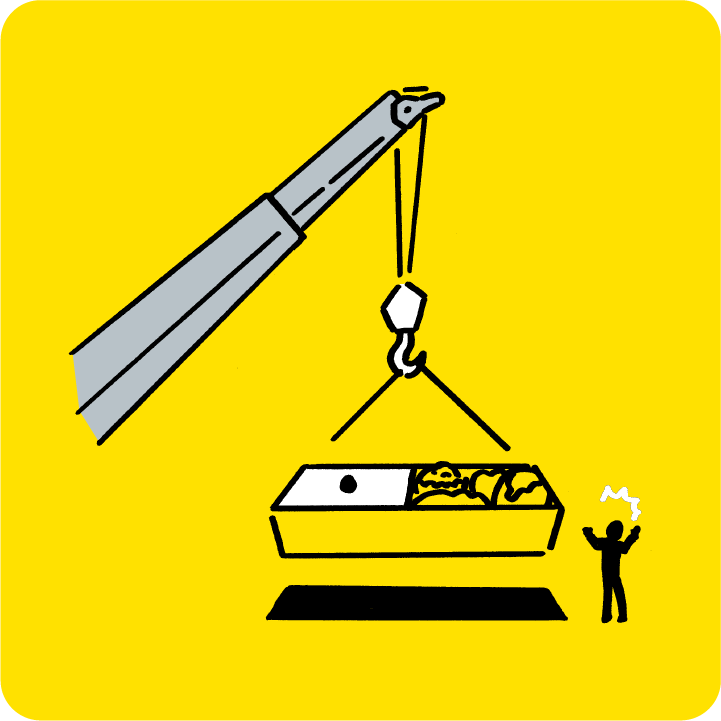
現場にワゴンで売りに来る
弁当屋のボリュームがハンパない。現場での休憩はだいたい1時間のところが多いので、みんな持参のお弁当やコンビニごはんを活用しています。中にはご近所の飲食店やお弁当屋さんがデリバリーしてくれる現場もあるのですが、だいたいどこもドえらいボリューム!おいしそうに食べる職人さんの笑顔や、「もっと食べたい!」というリクエストに応えるうち、ついつい大盛りになってしまうとか。
-
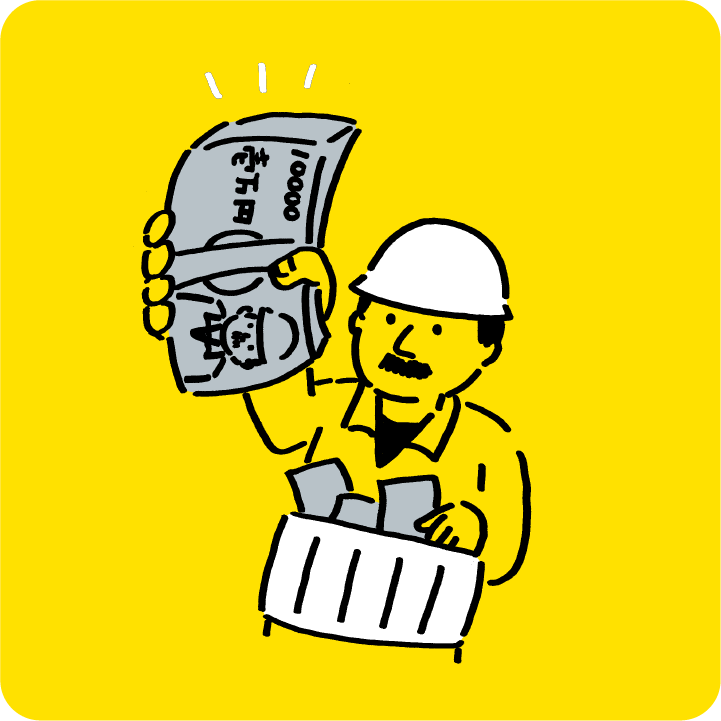
鳶の親方は、腹巻に
札束を入れて持ち歩いていた。昔から鳶職人は現場の責任者として働くことが多く、その親方ともなれば権限も絶大。しかしそれだけに面倒見もよく、時にはみんなに食事や酒をふるまうことも。そんな時のために、常にそれなりの金額を手元に置いておくのが親方衆の嗜みでした。腕一本、身体ひとつで勝負する職人ですから、自分の身体に密着する腹巻の中が、いちばん安全でいちばん安心できるお財布だったのかもしれませんね。
-
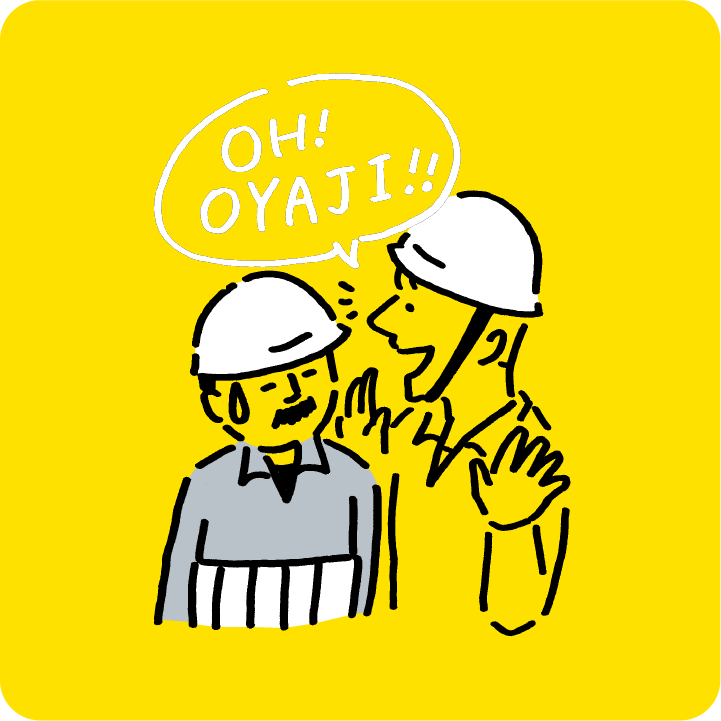
建設業界では、
親方のことを「おやじ」と呼ぶ。建設会社の社内や現場は、とても家族的なムード。もちろん仕事は真剣そのものですが、それ以外の時には趣味の話で盛り上がったり、一緒にごはんを食べたり、時には本気で意見を闘わせたり、本当の家族より濃い付き合いになることも。そんな時に、場を和ませたり治めたり、頼りになるのが親方。だからみんな、尊敬と親しみを込めて「おやじ」と頼るのです。
-
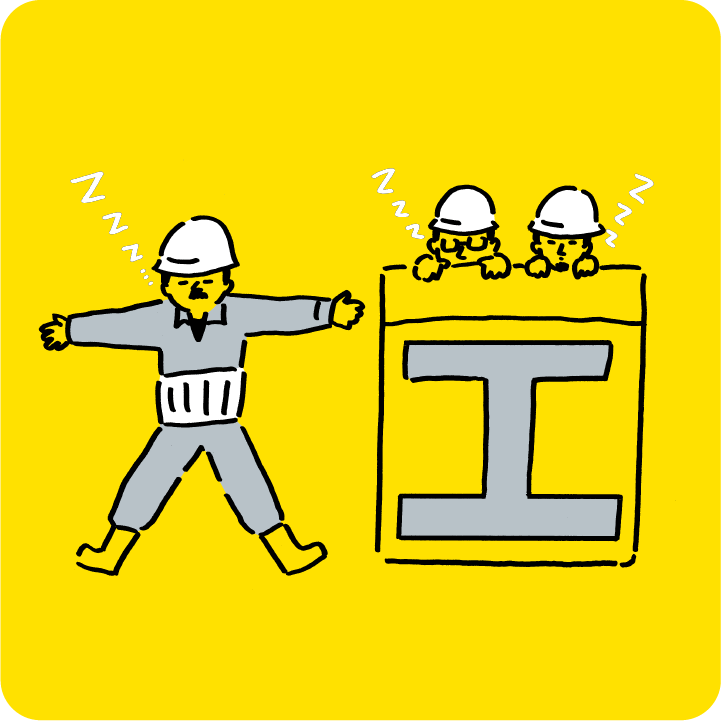
お昼の休憩時間は、
昼寝をする。昼食が済んだら、午後の仕事に備えてしっかり食休み、が現場の常識。早朝からの仕事だった場合には、本気寝に突入することも!? おや? 現場に職人さんの姿が少ないですね。事務所で休憩かな、と思いきや、ダクトの隙間や空調機の裏側などでお昼寝中。日陰の涼しいところ、静かな場所を知ってるんですね。猫みたい。13時前にはぱちりと目を覚まして、準備万端で午後の仕事です!
-

昔は、自分の子供が生まれたら
現場を3日間休まされた。昔は、出産はおめでたいことであると同時に「ケガレ」でもあったんですね。「血」が「ヒ」になり、いつしか「火」になって、「出産のケガレ(ヒ)に関係した者は火を高ぶらせる(火事を起こす恐れがある)から、仕事場に入ってはいけない」という言い伝えになりました。「生まれたばかりの子供と嫁さんとゆっくり過ごせるように」という出産祝い休暇として、復活すればいいのに(笑)。
-
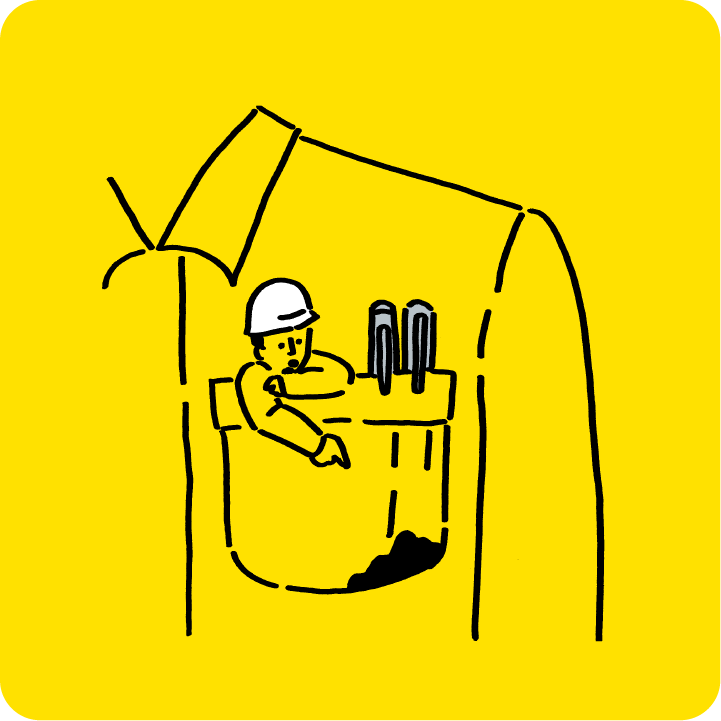
胸ポケットには、
ペンのシミがある。現場では、部材や図面に書き込みをすることも多いから、胸ポケットに筆記用具を挿しておくのがデフォルト。だけど、忙しさの中でついキャップをするのを忘れたり、芯が出たままポケットに戻してしまうこともたびたびなのです。かくしてユニフォームの胸ポケットには、黒や赤のシミがじんわり…。働く人間の勲章、ということにしておきましょう。
-
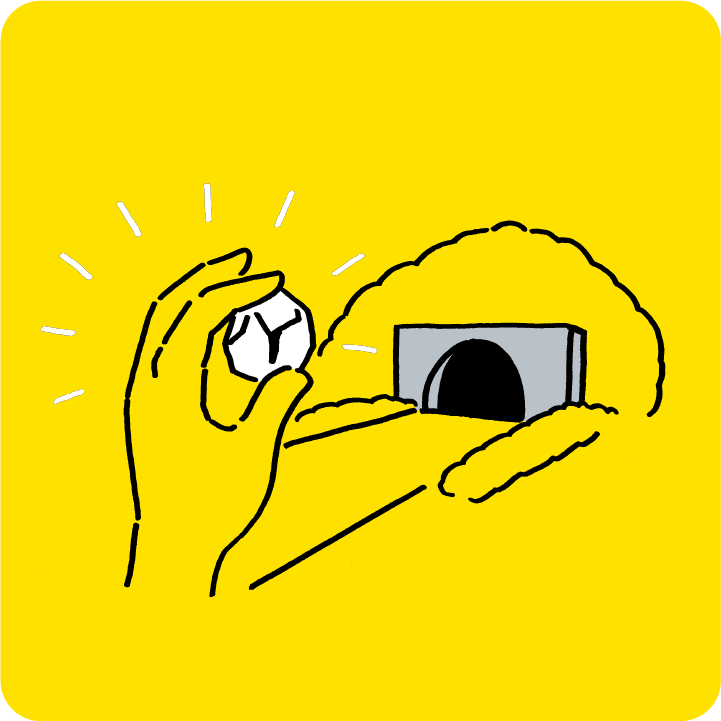
トンネルの貫通石は
安産のお守り。長い長い年月をかけて掘り進めたトンネルが、ようやく貫通したときのその石は、安産のお守りとして妊婦さんの枕元に置かれるのだそう。古事記の中で、神功皇后が遠征の際に得た石を出産のお守りとしたことに由来するもので、「トンネルが石(意志)を貫く」と学業成就のお守りとしても人気だそうです。
-

昔は、鳶の親方にお酒を持って行かないと足場を使わせてもらえなかった。
現場の長である鳶の親方に、ご挨拶がわりにお酒を贈り「何卒よろしく」という習慣が昔はあったんです。職人さんたちは目上歳上の人へのふるまいや上下関係に厳しいですから、侮りや軽んじの気持ちがあるとすぐに見透かされ、きっちりお灸を据えられました。その一端が、こうした習慣として表れたのでしょう。今でも、鳶の親方に対する畏敬の念は変わりません。お酒好きな人が多い、ということも、ね。
-


