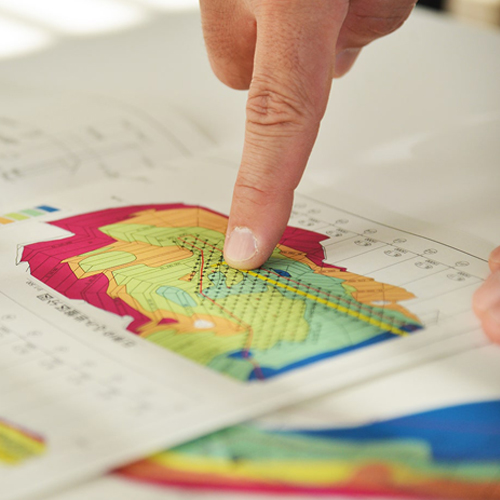清水建設入社後、巨大建造物に魅せられ「ダムスペシャリスト」になった男。
現在、岩手県盛岡市郊外で建設中の簗川ダムに携わる勝間田哲郎さんは、清水建設入社後すでに6つのダムの工事に関わった、ダムのスペシャリストである。「学生時代にダムのことなんて、まったく知らなかった。巨大土木構造物であるダムに興味を持ち始めたのは、中筋川ダムに赴任してからです。ただ、このダムはほとんど完成間近だったので、ダム建設に最初から携わってみたい」と会社へ希望を出す。
そうして赴任したのが岩手県大船渡市の鷹生ダムだった。大船渡市を流れる盛川流域は、豪雨の出水により下流の市街地において浸水被害が頻発していた。そうしたことから建設された多目的ダム建設に初めて関わり、勝間田工事長は清水建設のダムスペシャリストへの道を歩み始める。
「日本は国土が狭く、地形が急峻です。さらに梅雨や台風の時期に雨が集中するので、洪水が発生するかと思えば、天気が続くと渇水になる」と勝間田工事長は話す。森林面積が7割で、3割の平地のうち、なんと1割が氾濫危険区域に該当し、またその1割の地区に50%の人口が集中する日本において、ダムは必要不可欠なものなのである。「水を貯める、そして治水をコントロールする必要があるわけです」。
ただ、ダムはとても巨大な建造物であり、巨額のお金がかかる。そうそう工事があるわけではない。勝間田工事長は、東北だけでなく、九州、関西など、これまで6か所のダム工事に関わることができた。「時代もあったのでしょう。そういう意味ではやりがいのある仕事につけて達成感もあります」。手ぶり身振りを交え、ダム工事の難しさ、おもしろさを話す勝間田工事長の目はとてもいきいきとしていた。


「ただ、今のダム工事は、昔とは少しおもむきが変わってきています。周辺への配慮や環境への気配りは、以前の比ではありません。ダム工事周辺の住民だけでなく、動物や植物などにも細心の注意を払っています。清水建設内にも、そうした環境を専門とする部署があり、私たちも専門家の意見を受けながら、工事を行っています。稀少な植物の移植や、クマタカの抱卵時期と騒音工事が重ならないようにするなどはあたりまえで、われわれも、クマタカの巣立ちがうまくいくよう、見守りながらダム建設を行っているような感じですよ」と笑顔で話す勝間田工事長。
苦労も多いがやりがいもある、勝間田工事長はダム工事をそう捉えている。今後、建設現場へ来るであろう若者たちにも「巨大建設の魅力」を知ってもらえたら。鋭くもどこか優しい勝間田工事長の眼差しがそう語っていた(2019年取材)。